アスカの目が見えなくなった。
そうしていいものかどうか分からなかったが、僕はアスカを連れて病院を回った。
遠い国からやってきて急に目が見えなくなった留学生の友達がいる。
そう言ったら、母さんも父さんもアスカを引き取る事に同意してくれた。
もちろん、かなり姉さんが口添えしてくれたのは言うまでもない。
少し話が遠回りになるけど、僕と姉さんは名字が違う。
今だから言うけど、姉さんは血の繋がった姉弟ではない。父さんの大学の先輩の娘だったと聞いている。
姉さんのお父さん、葛城博士の研究隊が遭難して帰ってこなかった時、姉さんのお母さんは自殺してしまった。
残された姉さんを親戚の誰もが引き取れなかった時、父さんは黙って姉さんの手を引いて家に帰ってきたそうだ。
誰も自分を欲しがらないその時の心細さ。そして黙って手を引いてくれた父さんの温かい手。
家に迎え入れて、抱きしめてくれた時の母さんの涙。
姉さんはそんなものを思い出にして生きてきたと僕に話してくれた事がある。
「だからお願いします。アスカさんにも、寂しい思いをさせないであげて欲しいんです。」
そう姉さんが言った時、母さんはやっぱり涙をこぼして肯いた。
父さんは僕を見て言った。
「シンジ。同情だけではないな。」
僕はだまったまま父さんの顔を見た。
「はい。」
僕と姉さんは、たとえアスカが人間ではなくても自分の姉妹として受け入れようと思った。
僕は、姉妹としてでなく、もっと熱い想いがあったけれど。
医者はどこへ連れて行っても首をかしげた。神経系に異常は見られない。
それどころか、こんなに健康な状態の人も珍しいと、口を揃えて言った。
その度に僕はしつこく食い下がった。それではなぜアスカは見えないのかと。
結局人間の医者にはまったく分からなかったのだ。
「シンジ、もういいよ。これはきっと呪いの一つなんだ。」
病院からの帰り道、二人で休んだ町中の街路灯付きベンチで、アスカがぽつりと言った。
「呪いって何さ。」
「私が幸せを感じるたびに、それは壊れてしまう。いままで、いつもいつもそうだった。ギリシャでも、シラクサでも、カルタゴでも。」
アスカは白い杖を持った手をさすりながら言った。
「私には、この世に落ちてくる前の記憶が少しだけあるの。誰かを罵りながら深淵に落ちていく場面なんだけどね。」
俯いたアスカの陰が長く伸びている。その陰が花壇の花に届いている。
「わたしは、魔物。私の陰が届くところにいたものはきっと不幸になってしまうんだわ。」
見えない瞳を上げ、僕の方を見る。美しい、ターコイドブルーの瞳。
その視線が少し僕からずれている。その事がたまらなく胸を苦しくさせる。
「だから・・・だから神か何かが私を封印してランプや何かに縛り付けたのよ!」
「そういう事は、もう言わないってこの間約束したじゃないか。駄目だよアスカ、自分を責めたら。それに神様って・・・・実在するの?」
「分からない、そういう記憶はないの。」
アスカは弱々しくかぶりを振った。自分の気持ちを自分でも持て余しているようだった。
でも、アスカのような強い「魔物」を封印するのは、神様でもなければ無理なんだろう。
だが、その事自体が周りの人々を不幸にするとは思えない。
人々が不幸になったとすれば、それはアスカに頼り切って暮らして自滅していったからなんじゃないかと思う。
アスカは長い時間の流れの中でいろいろな人たちにその力を貸してきた。
封じた誰かが、もしアスカ自身の魔力を問題にしたのなら、魔力だけを封印すればいいはずだ。
だが魔力は封じられず、アスカの記憶だけを奪い、また行動の自由を奪う形を取ったのはなぜ何だろう。
その行動の自由にしても、僕のように電源を入れっぱなしにしたり、灯油を入れっぱなしにしている人間が持っているなら、
ほとんど拘束を受ける事は無くなってしまう。
魔力の行使にしても、持ち主、つまりはアスカの言うところの「御主人」の命令は聞かねばならないという約束があるだけだ。
命令なく魔力を行使してはならないという約束があるわけではないらしい。
少なくとも主人が死んだり、危機に陥った時、アスカは強大な魔力を振りかざす事があるようだ。
その時は往々にして意識を失っているようだが。
アスカと暮らし出してからの数ヶ月でアスカの魔力についてはこんな事がわかってきた。
だけど・・・・。
僕にとってはアスカは世界を手中に握れるだけの力を持つ兵器でもなければ、金の卵を産む鶏でもない。
見えなくなってしまった目に戸惑い、白い杖を握って不安に震えている、頼りなげな少女に過ぎない。
僕は、アスカの肩を抱き寄せた。そして暫く二人はじっとしていた。
一体これからどうすればアスカの目を直してあげる事ができるんだろう・・・。
その時僕の頭に一つの考えが浮かんだ。
「そうだ、加持さんだ。この指輪の文字を加持さんなら読めるかもしれない。」
この文字が古代フェニキア文字であると言っていた加持さんは読める可能性がある。
そうすれば、この事態についての対応も分かるかもしれない。
僕らは、加持さんのアパートを尋ねてみた。
しかし、管理人のオバさんが、加持さんは午前中に京都の実家に帰るといって出かけたことを教えてくれた。
「ああ見えてもとんでもないええとこの坊ちゃんらしいよ。ものすごい車が迎えに来たからね。」

 加持の実家
加持の実家しかしアスカは、視力といっしょにほとんどの魔力も使えなくなっていた。
「アスカ、君も何が書いてあったか聞きたいだろうけど、僕のお小遣いじゃ一緒に連れて行くのは無理なんだ。
ぼくがいってくるから、家で待っていてくれる?」
「シンジと離れているのはいやだけど、我慢する。でもこれを持っていって。連絡はこれでつけられると思うから・・・。」
そう言うとアスカはピンクの石がついたイヤリングを一つはずして僕に渡した。
「大きな魔法は使えないけどこの程度の事はできるわ。」
「じゃあ、とにかく一度家に戻ろう。」
僕はアスカの肩を抱えるようにして家路に就いた。寄り添うように帰ってきた僕らを母さんが迎えた。
「どうだったの、アスカちゃんの目は。」
「いつもの通り。どこも悪いところはないっていうんだ。」
「やっぱり指輪のかけらで眼球が傷ついたというわけではないのね。何が一体・・・。」
「かあさん。ちょっと京都に行ってきたいんだ。」
「あら、貴方も呼ばれているの?昼前にミサトも加持さんが迎えに来て京都に連れて行ったわよ。」
「ええ?姉さんも行っているの。」
「知らなかったの?向こうの御両親にお会いしてくるとかでね。」
つい4,5日ほど前に、加持さんは我が家を訪れた。
髭をきちんと剃り、トレードマークの長髪を奇麗に洗い上げ、こざっぱりと刈り込んであった。
そして姉さんと結婚したいと、父さんと母さんに申し込んだ。
母さんは、にこにこと加持さんと姉さんを見比べた。お似合いだわと何回も言った。
父さんは、じっと黙ったまま加持さんを見ていた。
口を開いたのはまず夕食を一緒に取りましょうという母さんの提案に答えた時。
「ああ、そうしよう。」
と言った時だけだった。そして僕をふりかえって言った。
「アスカも席に就けなさい。」
僕と姉さんがアスカを部屋に迎えに行った。
アスカは、ベッドに腰を下ろし、半分ブラインドを降ろした薄暗い部屋で音楽を聴いていた。
「え、だって私今目が見えないし、このうちの人ではないのに。」
アスカは最初拒んで行かないと言い張った。
「アスカ、君は他所の人なんかじゃないんだ。」
「そうよ。一緒に暮らし出したら、もう私達は家族なのよ。」
「そんな・・・・。」
「それに、ほんとの家族になるのだって、そう遠い事じゃないんじゃない?」
ぼくとアスカの二人は真っ赤になった。
「そんな!とんでも・・・ないです。」
「ね、ねえさんっ!!」
「あはははっ。アスカに会いそうな服を探してくるわ。」
姉さんは自分の部屋のクロゼットに消えた。なんか、性格変わったみたい。
「ほんとに、いいのかしら。主人のうちの婚約の晩餐に出席するなんてとんでもない事なのに。」
アスカは元気一杯の現代風の女の子なのに、妙に古めかしいところがあるのが、不思議な感じがしてしまう。
「それに、こんな身体だし。なんか不吉な感じがしないかしら。」
「馬鹿な事を言うんじゃない!」
思わず大声を出してしまう僕。びくっとアスカが身体を震わせた。
不安そうな顔をこちらに向ける。
あ、しまった。
「ご、ごめん。大声出して。でも今のはアスカが悪いんだよ。」
「うん、わかってる。ごめん、シンジ。」
僕はアスカの手をとった。白くて細い、優しい手だった。思ったより小さな、柔らかい頼りなげな手だった。
その手に、手を重ねた。
そして、僕はアスカの前に膝を突いて、包んだその手にそっと頬を押し当てた。
「シンジ・・・。」
「アスカ・・・。」
そうしていると、姉さんが部屋を出てくる音が聞こえたので、僕らは互いに手を放した。
「私が高校生のころの余所行きを少し出してきたわ。」
「シンジ、貴方が選んでくれる?」
アスカが言った。
「え、女の子の服なんて分からないよ。」
「野暮天なんだから、シンジは。女の子はね、好きな男の子の選んでくれた服を着たいものなのよ。」
「そ、そうなの?」
アスカは少し濃いばら色の頬をして肯いた。
アスカに似合う服・・・、僕は上品な紺色の、純白の大きなイタリアンレースのセーラー型の襟がついたワンピースを選んだ。
「いいセンスよ、シンジ。これは私が一番のお気に入りだったワンピースよ。」
姉さんはニコニコして言った。
「じゃあ、着替えたら連れて行くから、あなたは下で待っていなさい。」
下に降ろされた僕は、加持さんと父さん母さんで、たわいない話を続けていた。京都に両親が住んでいて古代史を大学で教えている事。
特に古代東地中海文明についての専門家である事。その影響でそれのレプリカのアクセサリーなどを販売したり制作したりするようになった事。
父さんも口は開かないがうんうんと肯いている。極端に口の重い父さんだけど、大分加持さんが気に入っているようだ。
そこに姉さんと、アスカが階段を降りてきた。
目をやった僕は、思った通りアスカが大変奇麗な事がうれしかった。
すぐに立ち上がって、歩きなれないアスカの手をとって、席まで連れてきて座らせた。
「ありがとうシンジ。」
見えない目で会釈して、微笑むアスカ。
胸元できらきらと小花の重なったネックレスが輝いている。そして額のいつもの真紅の宝珠とそれを止める細い金の鎖。
 アスカのネックレス
アスカのネックレス「素晴らしいネックレスだね、アスカくん。」
加持さんと父さんが同時に同じ事を口にした。
父さんは工学部の研究者だが素材研究にも力を入れているので金属類には目がない。
加持さんにとっては、多分興味津々の製品なんだろう。
初めて会った時から身につけていたのであまり気にしていなかったけど、こうしてみるとすごく手の込んだ細かいものだ。
それだけに普通の金の製品と輝きが違う。
「ありがとうございます。昔から伝わる大事なネックレスですので褒めて頂けてうれしく思います。」
その日の顔合わせはみんなが、気持ちよく楽しく過ごせた。
粗相をしないように、かろうじて残っているなけなしの魔力を総動員したのだろう。
アスカは次の日は熱を出して寝込んだ。
僕は、枕元で静かに本を読んで一日を過ごした。アスカがそれを望んでくれた事が嬉しかった。
時々氷枕や、額のタオルを取りかえると、うつらうつらしていたアスカは気がついて僕の名を呼び、それに答えると安心してまた眠るのだった。
顔を火照らせているアスカの寝顔を時々見ながら、僕は夜遅く迄そうしていた。
アスカには悪いけど幸せな気持ちだった。
京都に着いたのは、夜の9時過ぎだった。
加持さんが蹴上の都ホテルをとっておいてくれたのでそこに入った。
姉さんは今日加持さんの家に泊まるので、明日一緒に帰ろうと言う事になっていた。
明日、午前中に加持さんのお父さんが、指輪の文字の解読をしてくださると言う。申し訳ないと思うけどアスカの為に無理を言おうと思う。
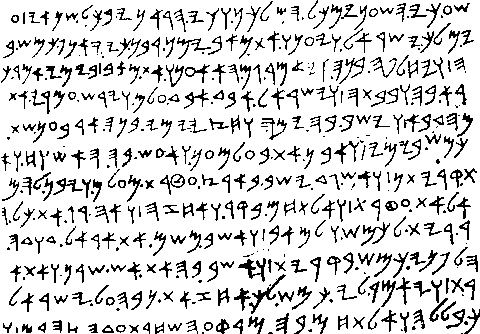 古代フェニキア文字
古代フェニキア文字加持さんのお父さんは加持さんをもっと優しくしたような、笑みを絶やさない方だった。
じっくりと指輪の裏側に刻み込まれた消えかかった文字を時計職人がはめるようなルーペを片目にはめて見詰めている。
時々ため息をついて目を離し、細かい砥粉のような粉をかけて少し磨いてていねいにふきとり、手元の手帳に何かを書き込んでいく。
「父さん、フェニキア文字であるのは間違いないだろう?」
「ああ、そして驚くべき事におそらくクレタ線文字Aと思われる文字がそれ以前に書き込まれている。」
目をもみながら加持教授は答えた。
「おそらくは線A文字で書き込まれたものが摩耗して読み取れなくなった為に更に上から同内容を刻み込んだのだな。」
「あの未解読文字が・・・・。」
加持さんが絶句した。
「このリングの考古学上の価値は、計り知れんな。紀元前12〜3世紀にフェニキア文字が刻み込まれ、おそらくその前に溯る事10世紀。
クレタの文明は少し前方にずれ込む事になりそうだ。おそらくは紀元前20〜23世紀頃に作られた指輪なのだろう。」
気が遠くなるほど昔のものであるようだ。
「さて、内容を読んでみたがこういうことが書かれている。
『 この石を作りしものは告げる、赤い目の天使に。青に会っては青、赤に会っては赤の汝が姿をあらわすと。』・・・と。
『 猛き心勝れば汝かくのごとき有て成り。慈き心勝らば汝そのごとく有りてなり。』
『万に万のさらに万の人々と共に汝滅ぶべし。またあれかし万に万のさらに万の人々と共に汝栄えるべし。』
これは呪いと、弥栄の詩が一緒に刻み付けられた古代に良く見られる寿呪の文句だね。」
そうだろうか。
こんな簡単なものでアスカに何か影響を与えるような事が起こり得るだろうか。とてもそうは思えない。
「ラルク、バルエストノモス。エルクエムラガシュ。ストロロバス、エン、コンサイティアストゥルガルエンマカテウオン。ウィクエンマッハデオヤーガ。」
「なんだ!?」
加持さんが天井を振り仰いだ。部屋中に聞きなれない音韻が満ちて、物凄い圧力で僕らの体を締め付ける。
「うっむううっ!!」
その声は、まるで化学合成された分子が重合体を作るように、重なり数倍に膨れ上がり、急速に大きくなっていく。
それが僕にもはっきり分かった。