「え?そうかしら。」
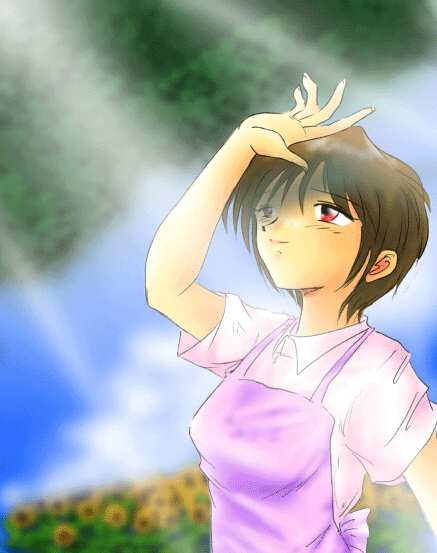
ユイ母さんは、何も聞こえないほどの蝉時雨の下から、その大きな曲がった栃の木を見上げた。
僕は一生懸命さがしたけれどさっぱり見えない。泣き声は聞こえたような気がするけれど。あっ。
「ほら、あそこの大きな枝の上から聞こえるんだよ。猫かな。あ、今なんか動いたよ。」
「あなた。ちょっと見てくださいな。しんちゃんが何かが木の上にいるって言うんですけど。」
芝生を刈っていた父さんが、首にひっかけたタオルで汗を拭きながらやってきた。
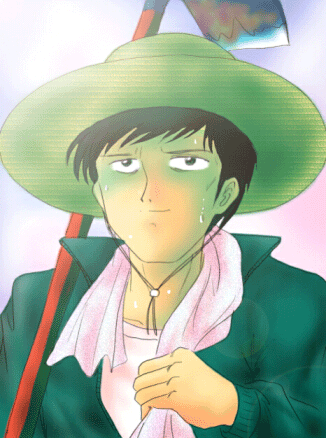
「うーん?よくわからんな。」
父さんは幹に手をかけると、ひょいひょいと木を登って繁みの中に潜り込んでいった。
「おとうさーん、何かいたぁ?」
「あなたー、大丈夫ですか。」
「今、降りていく。」
声が聞こえたと思ったとたん、ザザザッと繁みを突き破って父さんは飛び降りてきた。
「わあっ!!」
「きゃあ。」
「ははは。びっくりしたかな。」
爽やかな笑顔から白い歯を光らせて笑った。父さんかっこいい!
その時、父さんが小脇に何かを抱えているのに気が付いた。
「父さん、何を抱えてるの?」
「これか?これが泣き声の正体だ。よおし、もう大丈夫だ。」
あかいTシャツに、ジーンズの短パンをはいた、茶色い髪に野球帽。
そんな格好の子を父さんは降ろして立たせた。
その子は、一回しゃくりあげると、周りをキロキロと見回した。
「あらあ、子供だったのね。あなた、どこのうちのお子さんなの?シンジと同い年くらいかしら。」
その子は敵意のこもった目で母さんを見詰めていた。
母さんが手を差し伸べてもその分後ずさりをして近寄ろうとしない。
「君、大丈夫?何処か怪我してない?」
僕はそーっと近づいて言った。
その子は身構えたが自分と同じくらいの大きさの僕に対しては逃げようとはしなかった。
「きみ、なんて名前?」
僕はゆっくり話し掛けた。
「近寄るんじゃない!」
「でも、そこ、血が出てるよ。」
腕の内側。落ちまいとして必死に木にしがみついていたのだろう。擦り剥けて血が滲んでいる。
膝の内側にもくるぶしにも、同様の傷があって血が細い線になって擦り傷から垂れていた。
「こ、こんなの怪我のうちに入るもんかっ。」
「だめだよ消毒しなくちゃあ。化膿したらたいへんなんだよ。」
「そ、そーどく?かのー?なによそれ・・・。」
「そこで待ってるんだよっ。」
家の中に飛び込むと、木の箱の救急箱を持って、その子のところに走っていった。
「あらあら・・・、いつもの泣き虫さんが。」
母さんがが目を細めてみている。父さんも少し驚いたような表情で僕を見ている。
「ほらっ、君、こっちへ来て!」
「う、うん・・・。」
「ちょっとしみるかもしれないけど我慢するんだよ。」
「うん。」
気おされたのか、素直に消毒されようとしたその子は、僕が最初の消毒綿を傷につけた途端に
うっと顔をしかめた。
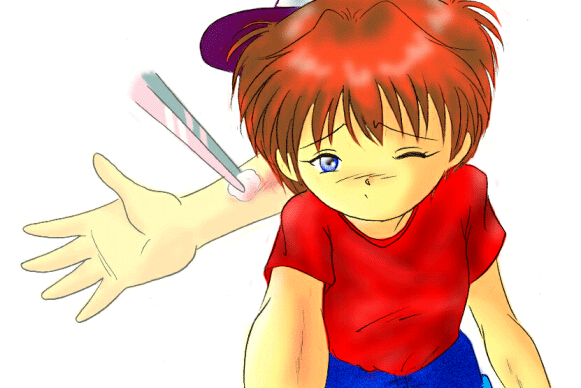
「いたああーい、かえって痛いよ。」
慌ててふーふーと僕は息を吹きかけた。
「まだ痛い?」
「ううん?そうしてもらったら痛く無くなった。」
「僕も怪我すると、母さんにこうしてもらうんだ。」
「優しいお母さんなんだね。」
「ぼくはね、シンジ。君の名前は?」
せっせと消毒してはふーふーと息を吹きかけながら僕は言った。
その子をもてなそうと思ったらしい母さんが、台所で西瓜を切っている。
「私はアスカ。」
「アスカ?女の子みたいな名前だね。」
そのとたん、その子は真っ赤になって僕をひっぱたいた。
そしてあっという間に、消えた。僕が泣きそうになりながら目を開いたときには
其処にはもう誰もいなかったんだ
「どうしたの?慎二。あら、あの子は?」
「女の子みたいな名前だなって言ったら、急に僕をひっぱたいてどこかへ行っちゃった。ぐす。」
「あらあら。それは怒られて当たりまえねえ。」
「ええ〜、どうしてさあ。」
母さんが笑い出した。父さんが芝生を刈る手押し車の音ががらがらと響いていた。
「あの時の木登りあっちゃんだったのかあ。小さい頃会ってたんだね。」
「ちょっと待ってよ。それじゃ私がお転婆なだけだったみたいに聞こえるじゃない。」
明日香はムキになってテーブルをバンと叩いた。
麻耶が作った冷や麦のボールが、ちょっと飛び上がった。
「よしなさいよお。で、どうして碇くんは穴掘りシンジなんて呼ばれていたわけ?」
「せやなあ、そのあたり詳しゅう聞きたいですな。」
ヒカリさんとトウジがにやにやしながら焚き付けるように言った。
「うん、それなんだけどね、聞いてよ。慎二ッたらさあ。」
こんこん・・・ごんごん!!ばんっ。
ききーっと、わずかな音を立てて窓が開くと、寝ぼけがおで布団から頭を出すシンジ。
朝の冷たい空気流れ込んでくる。朝のきらきらした光の中に誰かがいて、窓のさんに腰掛けている。
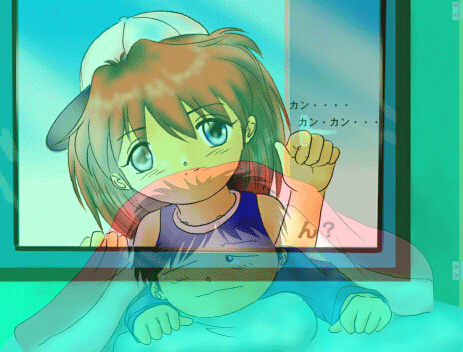
「おはよう、しんちゃん。」
「きみ、だれ?」
どこかで聞いた声。僕は手のひらで朝の光を遮りながら尋ねた。
「何よ。もう忘れたって言うの。失礼しちゃうわねえ。」
「あ、その声は、きのうの・・・あすかちゃんだね?」
光の中から、ずいっと女の子が現れた。今日は白い淵の紺色ランニングと、ピンクのスカートをはいている。
「あたり。」
「今何時なの?」
「6時。ラジオ体操に行くところなんだ。おまえ・・・あんたも誘ってやろうと思ってさ。」
「ここ、2階だよ、どうやって・・・。」
「これこれ。この大きな朴の木、登りやすいでしょ。」
「枝を伝わって来たの?」
「そ。さあ、早く着替えて。いくわよっ。」
「な、何に?」
「だかーらー。ラジオたいそうにきまってるじゃない。
「ええーーーっ!」
正直言うと、僕はこの手の行事がだいっきらいだっだ。だから大喜びで「合宿」にやってきたのに。
「いやなの?せっかくこの辺のお友達を紹介しようと思ったのにな。」
「と、ともだち?」
これは魅力的な提案だった。いくら内向的な僕といえどもここへ来てから10日近く。もういいかげん
本を読んで、たまにお母さんと海で遊ぶだけの生活にも飽きが来ていた。
「男の子もいる?」
「もっちろん。私以外はほとんど男の子よ。女の子はちょっと乱暴な遊びしたり、ちょっと怪我したりすると
すぐ泣くしさあ。めんどくさいじゃない。」
アスカは自分が男の子みたいなことを言う。
「きょうはみんなで秘密基地を作るんだよ。昨日あの木に登っていたのもあの木の調査のためだったんだ。」
「へえ、そうだったんだ。木の上に基地を作るの?」
「そうだったんだけど、あそこは足場が悪かったな。だから、また別のとこを探さなくちゃ。」
「ねえ。地下基地って言うのはどう?」
「地下基地?」
「うん、あなをほってさあ、その中にいろいろな道具をを入れるの。テレビとか、れーぞーことか、たたみも。」
「すごいっ。それはすごいねえっ。そうか、地下ならいくらでも広げられるしね。」
アスカはすっかりその考えにとりつかれたみたいだった。
僕はすぐ着替えて、外に飛び出していった。門からの階段を駆け降りたところにアスカが待っていた。
「いこう!」
ラジオ体操の後みんなとの顔合わせはすぐに済んだ。アスカがいいといえばなんでも通るみたいだった。
「ねえ、アスカちゃん。ここら辺の子供たちってみんな髪の色が違うんだね。わかりやすくていいけど。
アスカはちょっとびっくりした様に振り返った。
「え?あんたみんなの色が分かるの?」
「うん。あの大きな子は黒。木の下にいる子は赤。君は明るい茶色。向こうに座っている子は銀色。」
「へ〜〜〜。みんなわかるんだ。」
「ほら、アスカちゃん、こいつが「見通すもの」って奴じゃないのか、爺ちゃんの言ってた・・・。」
隣に立っていた黒い毛の子がささやいた。
「そうかもしれないね。ほんとにいるんだねえ。」
「え?なんのこと?」
「うん、いいのよ。さてそれじゃみんな聞いて。シンジから面白い考えが出たの。地下基地を作ろうって事なんだけど。」
「へぇ 〜、地下基地かぁ。木の上より大きくできそうだな。」
「木の上の基地は地下基地ができたら、見張り台としてつくるんだよ。それなら小さい木でもできるでしょう?」
みんなが賛成したので、さっそく場所を決めることになった。この別荘の裏山に小さな川が流れてるとこがあって
其処に古い穴があるので、それをもっと広げればいいということに。
「じゃあ、これから早速出かけよう。」
僕らはさっそく出発した。途中の山道は面白いことでいっぱいだった。アスカはいろいろなことを知っていた。
「ほらこれ。」
ちぎってくれた細かい毛の生えた小さなピンクの実は、甘酸っぱくて美味しかった。
「こけももっていうんだよ。こっちはね、グミ。これは木苺。橙色のと赤いのがあるんだ。」
この白いきのこは生のままでも食べられる。この優しい感じの草の根は甘い。この花の花びらは蜜がある。
みんなも歩きながら、口の周りを紫色にして何か食べているている。
桑の実を山ほど採ったからだ。僕のワイシャツも胸ポケットが紫色に染まった。
お母さんに持っていこうと思っていっぱい詰め込んだから。
アスカがナイフで木の皮を切り取った。
それを石で叩いて水を掻けながら指でひねっていると何かべたべたしたものが残った。
「これはなに?」
「しらない?これで鳥や虫を採るんだよ。」
其処に生えていた竹を腰に差していた鉈で倒すと、器用に枝を全部払ってしまって先端部を切り落とす。
そのねばねばをたっぷり塗り付けると3,4mくらいの長さでになった。
その竿を振り回すと、高い位置にいたセミをたちまち10匹ほどくっつけてしまった。
「みんな、とれたよ!」
男の子達はわっと集まってきてセミを口の中に放り込んでしゃりしゃりと食べてしまう。
「セミって、食べられるの?おいしい?」
僕はこわごわ聞いた。
「うん、幼虫ほどじゃないけどけっこういけるぜ。」
食え、というように一匹差し出されたけどそれはさすがに遠慮した。
幼虫は焼いて食べるそうだけど、そっちも食べたくはない。
小鳥も何羽か捕まえた。
「弁当だ。」
そういうと、アスカ達はみんなポケットに小鳥を取れただけぎゅうぎゅうと押し込んだ。
川に出ると、下流に石をいっぱいならべてかわをせきとめるような形にした。
一人の男の子が上流に走っていった。
「なにをするの?」
「モミを撒くのよ。」
「もみ?」
「サンショやヨモギの粉のことだよ。」
アスカが教えてくれた。しばらくすると、ぷかぷかと次々に魚が浮かんできた。
みんなで歓声を上げてその魚たちをわしづかみにする。
それのえらと口を、つぎつぎに川のほとりに生えているすすきや笹の茎に通す。
僕はもうすっかり興奮してみんなと一緒に魚を担いで大声で歌を歌いながら山道を歩いた。
見るものが、聞くものがみんな僕には新鮮だった。
「ここがそうだよ。」
それは大昔の人が作った洞穴のようなところだった。確か、シェルターとか防空壕とか言うものの遺跡だ。
でもすっかり埋もれてしまっていて、2,3mも行くと行き止まりになっている。
「これをもう一度掘れば、立派な基地になるんじゃない?」
アスカは、僕の耳に口を寄せて言った。確かにこれならすごく立派なのが作れるに違いない。
持ってきたシャベルや木の棒で、溜まっていた土を突き崩していく。
アスカや何人かの子は腰につけていた分厚いナイフで掘っている。
僕はそのナイフがうらやましくて、ちらちら見ながら一生懸命穴を掘った。
次第に夢中になってきて他の事は目に入らないくらいになった。
「ほら、これ食べなよ。」
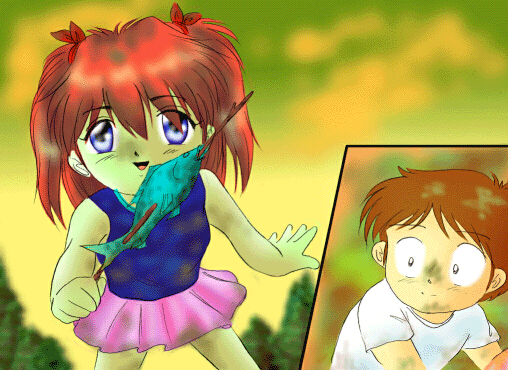
川で取った大きな鮎か何かを焼いた奴を手渡されたとき、僕は初めて顔を上げた。
土だらけの顔のアスカが笑っていた。
「あれ?みんなは?」
「もうとっくに飽きて帰っちゃったよ。あんた、いくら呼んでも振り向きもしないんだもの。」
焼き魚をかじると、口の中にこおばしい香りがいっぱいになった。
続けて、アスカは竹筒を僕に手渡してきた。
「なにこれ。」
「なにって、水よぅ。あんた何にも知らないんだね。」
頭に刺さっている栓を抜くと、冷たい水が零れてきた。僕は慌てて口をつけて飲み干した。
「つめたいや。それにすごくおいしい。」
「さっきこの上の泉から汲んできたばかりだからね。後で連れてったげるよ。顔真っ黒だし。」
「君だって土だらけだよ。」
「そう?でも大きな穴がほれたね。」
アスカはにいっと笑った。
改めて二人で掘った穴を見た。かがんで入れるくらいの穴が奥行き3mくらいあって、
その後は少し広くなって小部屋のようになっている。立つと天井に頭をぶつけるくらいの高さだ。
丸い石をもち込んで床の赤土をたんたんと叩いて固めていく。その上に杉の葉を敷き詰め、
さらによく乾いた木の葉をいっぱいに撒いた。寝転がるとひんやりして気持ちがいい。
「今日はもう帰らなきゃだけど、明日はもう少し入り口を広げようね。」
「うん、うちにある小さなテーブルを持ってこよう。
日はもう西にすっかり傾いて、ほおずきの実みたいにぽってりと空に浮かんでいた。
僕らは泉に行って顔や手足を洗った。それから、アスカに案内してもらって家まで帰ったのだった。
それから僕らは毎日毎日一緒に遊んだ。森を抜け、山を走り、海に飛び込み、川で泳いだ。
「生まれて初めての夏休み」のような日々を、僕は過ごした。都会では到底知る事のできない冒険と危ない遊びの日々。
ロケット花火の水平撃ち、ナイフを使っての木彫りや竹細工。子供の集団で駆け回るのはほんとに楽しかった。
高いがけをよじ登り、高い木のてっぺんから遠くを眺め、草に腿や頬をいつのまにか切られ、裸になって相撲をして
傷だらけの真っ黒になった。真っ暗になってから毎日帰る家。帰るたびにお母さんの心配そうな悲鳴が上がる。
でもお父さんは何も言わなかった。年かさの友達の言う事だけはしっかり聞いて守れ、といっただけだった。
はまぼうふうを摘むのを手伝ったり、魚や貝をいっぱいとって、分け前の配分でお母さんに喜ばれた。
山には食べられるものがいっぱいあって、それを食べながら自然のいろいろな事をアスカに教わった。
鳥もちはミルクカンいっぱいに溜まり、作り方を教えてもらったモミや、怪しげな血止めの薬草や、お腹痛のとき食べる草の
在庫も箱いっぱいになった。僕の部屋はナイフで作った竹細工や木彫りのおもちゃが転がるようになった。
貴重品のラムネ玉が、机の引き出しに溜まった。(海岸の店で買ったラムネのビンを割って取り出した奴だ。)
僕はやはり一番秘密基地作りに熱中していた。アスカは見晴らしのいい気の上に見張り台を作って昼寝していた。
仲間たちは僕らを穴掘りシンジと、木登りあっちゃんと呼んでからかった。
「素敵な話ね〜。そうやって幼い日の二人は一緒に一夏を過ごして今また巡り合ったのねえ。
いままた、そのことを思い出して、新たな思い出となったというわけね。」
「ええお話やのう。めでたしめでたしというわけやなあ。」
僕らの話は其処で途絶えた。
もうお仕舞だと思った洞木さん達はうるるな目になって言った。トウジも少し感動したみたいだった。
「う、うん。」
「まあ、そういうことよね。」
歯切れの悪い僕ら。トウジ達は気づかなかったが、そのままだったら二人がお互いを忘れてしまう事もなかったろうし、
こんな風にあっていたのに気づかない事もなかったろう。
そうその後、僕らがその夏以降、別れ別れになった原因となる事件があったのだ。
その夜ごちそうをたら腹食べて、トウジは豪快に爆睡してしまった。
明日香と一緒の部屋にいた洞木さんも、おしゃべりの途中で、こっくりこっくりし始めてそのまま眠ってしまった。
二人にとっては、大変な一日だったのだから無理もない。
僕と明日香はベランダに並んで腰を下ろしていた。
「びっくりした。こんなに久しぶりに会ってたなんて。」
「ぼくもさ。どうして君の事をずっと忘れていたんだろう。」
「私も、急に思い出したのよ。こういうことってあるのかな。」
「まるで、忘れさせられてたみたいだ。」
僕は夢中になって穴を掘りつづけていた。夏休み中かけて作った基地は最初の日から見ると
ずいぶん広くなっていた。太い枝を持ち込んで壁を補強し、小さな家具やゴザまで持ち込んだ。
そんなある日・・・。
地面の中に張った、菩提樹の大きな根を避けながら掘り進んでいた僕のシャベルに、何か硬いものがこつんと当たった。
なんだろ。その周りを掘り起こすとそれは、丸い鍋のような形をしていた。白い石のようなそれは薄くて、
繋ぎ目がちらちらと走っていた。
「これって・・・・。」
僕はその不思議な形のものを持って、いろいろなものを想像した。
「それは人間の骨だ。ちょうどおまえくらいの子供の頭の上半分の骨だな。」
誰かが僕の後ろに立って言った。